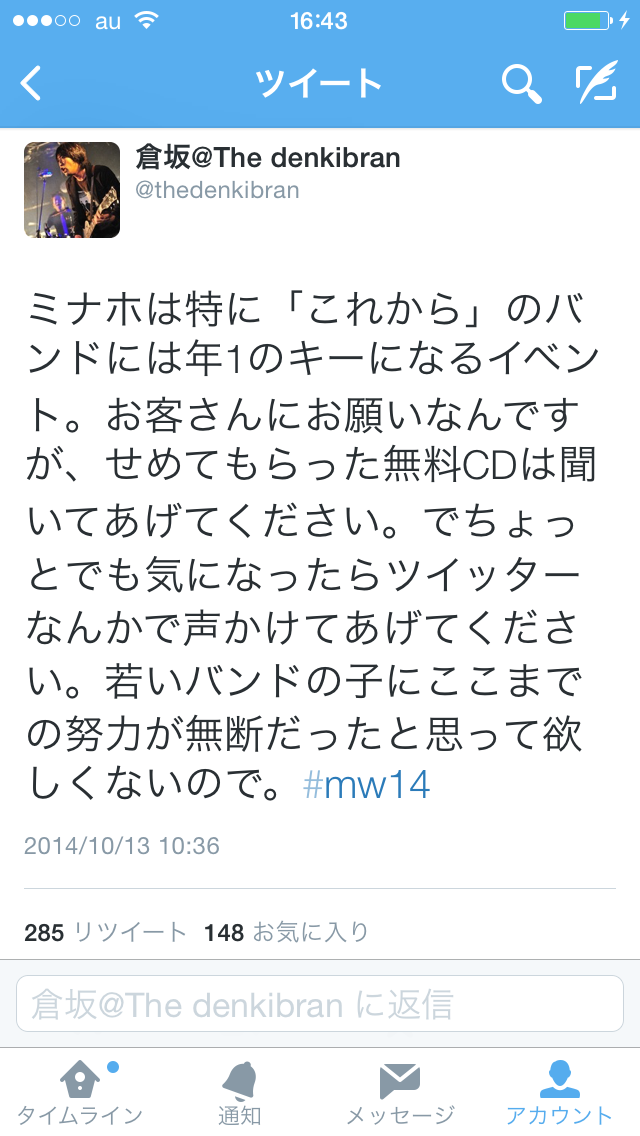注文 お客さんの多い 料理店 ライブハウス
2人の若いアマチュアミュージシャンが、すっかりバンドマンの体をして、大切な楽器をかついで、こんなことを言いながら歩いていおりました。「ぜんたい、ここらのライブハウスは怪けしからんね。客なんて1人も居やがらん。なんでも構わないから、たくさんのお客さんの前でライブをやってみたいもんだよ。」
「うん。満員のお客さんの前で演奏できたら、ずいぶん痛快だろうねえ。満員のお客さんの前でライブが出来れば、すぐに僕らも人気バンドになってメジャーデビューだってできるだろうねえ。」
それは東京ではないけど、地方と呼ぶには少しだけ都会で、たくさんのライブハウスが乱立している街でした。
バンドをはじめたての彼らがどこのライブハウスに出演したらいいのか…ちょっとまごついてしまうぐらい、街にはたくさんのライブハウスがありました。
それに、あまりにたくさんのライブハウスがあるので、そこに無計画に出演した彼らは、一ヶ月に6本ものライブをこなし、最初の頃は付き合いで見に来てくれた友達もやがて誰も彼らのライブには来なくなってしまいました。
「今月だけで、じつに僕は、三万円の損害だ」と一人のバンドマンは言いました。
「僕は楽器の修理代も今月はかかったので五万円の損害だ。」と、もひとりが、くやしそうに、頭をまげて言いました。
出演するライブハウスから提示されたチケットノルマの枚数に満たなかったチケットを自分達で買取ったり、練習するためのスタジオレンタル代金、レコーディング費用、楽器の購入費用、打ち上げや付き合いのための諸経費などなど。
そう。はじめたての夢見るアマチュアバンドはお金がたくさんかかるのです。
はじめのバンドマンは、すこし顔いろを悪くして、じっと、もひとりのバンドマンの、顔つきを見ながら言いました。
「僕はもうバンドを辞めようかと思う。」
「ああ、僕もちょうど飽きてきた頃だし、辞めようかと思う。」
「そいじゃ、次のライブで解散しよう。なあに、まだはじめたばかりのバンドだ。今辞めたって何も影響はない。」
「そうだね。また別のバンドでもはじめたら良い。そのバンドで売れたら結局おんなじこった。では解散しようじゃないか」
ところがどうも困ったことに、すぐに解散するつもりが、一度出演したたくさんのライブハウスからイベント出演の誘いが来てしまい、それを断りきれずに、いっこうにいつ解散したら良いのか見当がつかなくなってしまいました。
辞めると切り出そうとすると、君たちには才能がある、今はまだ人気はないけどいつかきっと人気が出るはず、と2人のバンドマンは言われ、その度にその気になってしまうのです。
「なんだか勢いで今月はツアーにも出てしまったけど、ライブをやってもギャラは出ない。交通費だけでもかなり出費でお金的に限界だ」
「僕もそうだ。もうあんまりライブはしたくないな。」
「うん。ライブはもうしたくないよ。ああ困ったなあ、でも人気は出て欲しいなぁ。」
「人気者になりたいもんだなあ」
二人のバンドマンは、ある日のライブの翌日、街を歩きながらこんなことを言いました。
その時ふとうしろを見ますと、立派な一軒のライブハウスがありました。
そのライブハウスの入り口には
LIVE HOUSEライブハウス
WILDCAT HOUSE
山猫小屋
という札がでていました。
「名前はよく聞くライブハウスだ。○○や○○なんてバンドも出演しているライブハウスだ。こんなところにあったんだ。一度、出演させてもらおうじゃないか」
「おや、こんなとこあったんだね。しかし僕達のバンドで出演できるのだろうか」
「もちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか」
「入ろうじゃないか。僕は本当はバンドが辞めたいわけじゃなくて、やっぱり本音ではバンドは続けたいんだ。」
二人はライブハウスの入り口に立ちました。入り口は白い瀬戸の煉瓦で組んで、実に立派なもんです。
そして頑丈そうな年季の入った防音扉があって、そこに金文字でこう書いてありました。
「出演バンド募集。ジャンルや上手い下手は問いません。プロになりたい方、どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません」
二人はそこで、ひどく喜んで言いました。
「こいつはどうだ、やっぱり世の中はうまくできてるねえ、今までのバンド活動ではなんぎしたけれど、今度はこんないいこともある。きっとこのライブハウスに出演していたらプロになれるんだぜ。」
「どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。」
二人は戸を押して、なかへ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。その防音扉の裏側には、金文字でこうなっていました。
「ことにやる気のあるバンドや、若いバンドは、大歓迎いたします」
二人は大歓迎というので、もう大喜びです。
「君、僕らは大歓迎にあたっているのだ。」
「僕らのバンドはやる気もあるし若い。両方兼ねてるから」
バンドの出演日が決まる。
ライブハウスの奥に進みスタッフに事情を説明すると、すぐに彼らのバンドの出演日が決まりました。来月の○月○日です。
「どうも変だな。僕達のバンドの曲も聴いてないのにすぐにライブの日が決まるなんて。」
「これはアメリカ式だ。アメリカのライブハウスなんてみんなそうさ。ライブで実力を見るんだよ」
そして二人は帰り際、扉をあけようとしますと、上に黄いろな字でこう書いてありました。
「当ライブハウスはお客さんの多いライブハウスですからどうかそこはご承知ください」
「なかなかはやってるんだ。やっぱり○○や○○なんて人気バンドも出演しているからね。」
「それあそうだ。見たまえ、東京の有名なライブハウスだって大通りにはすくないだろう」
二人は言いながら、ライブ当日をむかえました。
楽屋からステージに向かうその扉の裏側に
「お客さんがずいぶん多いでしょうがどうか一々こらえて下さい。」
「これはぜんたいどういうんだ。」
ひとりのバンドマンは顔をしかめました。
「うん、これはきっとお客さんがあまり多くて客席が騒がしくなるけどごめん下さいとこういうことだ。」
「そうだろう。よし、がんばって良いライブをしようじゃないか。」
ところがステージに出てみると、客席は伽藍としていて1人もお客さんはいませんでした。
演奏時間は各バンド15分と少し短めではありましたが、12バンドものバンドが出演していたイベントであったにも関わらずです。
その日のライブ終演後、次のライブもすぐに見てみたいとの事で、次の出演日も決まりました。
「次のライブこそはしっかりやってください。次こそは楽しみにしていますよ。」
と帰り際にスタッフに声をかけられました。
「これはどうももっともだ。今日のライブだけで僕達の実力を判断されたら困る」
「お客さんの多い人気のライブハウスだ。きっとよほど人気バンドたちが、たびたび来るんだ。僕らも早く人気バンドに追いつかないと。」
そして2人は、さらに練習に身を入れて万全の体制で次のライブに臨みました。
次のライブ当日。
今回のイベントの出演は8バンド。総数は前回よりもやや少なめで、今回のライブでの演奏時間は20分。
今回のライブでも客席を見渡しても、お客さんの数は前回よりも多かったものの、それでも片手で数えられるほどの人数でした。
「お客さんの多いライブハウスのはずなのに、これはいったいどういうことなのだろうか。」
ライブの終演後、二人はびっくりして、たがいの顔を見合わせました。
ライブハウスの店長とおぼしき人間が言いました。
「うちのライブハウスで自主企画イベントをやってみないかい。バンドだけでの自主企画イベントが厳しいなら、ライブハウスと共同企画イベントでもかまわないよ。」
まだバンドをはじめたての彼らに、自主企画イベントは荷が重いと思われましたが、ライブハウスとの共同企画なら心強い。
彼らはこれをチャンスと思い、ライブハウスとの共同企画を開催することにしました。
「イベントで一緒に共演の誘いをする友達のバンドがいてないのなら、ライブハウスからも紹介するよ。気軽に相談してください。」
「なるほど、それなら安心だ。」
「ライブハウスが協力してくれるなら心強い。」
月日は流れ、企画イベント当日。
元々バンド友達の少なかった彼らは、一緒に共演するバンドを連れて来ることができませんでした。
ライブハウスから一組のバンドを紹介してもらったので、合計2組での2マンライブイベントを開催することになりました。
「2組でのイベントにはなってしまったけど、このライブハウスにレギュラーで出演してくれるバンドを一組紹介してくれたので心強い。」
「うん。なんてったてお客さんの多いこのライブハウスにレギュラーで出演しているバンドだからね。」
客席を見渡すと、お客さんの数は普段よりも多いもの30人ほど。
満員で300人入るこのライブハウスのキャパシティでは少し淋しい人数ではありました。
「おかしいな。今、客席にいるお客さんはみんな僕達の顔見知りや、僕達のバンドのファンばかりだね」
「うん。だけどライブハウスから紹介してもらったバンドだ。文句は言えないよ。きっと共演バンドのお客さんは後で来るんだよ。」
けっきょくイベント終了後まで、その30人から1人もお客さんが増えることはありませんでした。
「おつかれさまでした。イベントも無事に成功したし次はワンマンライブですね。レコード会社や事務所の関係者もたくさん呼んでおきますよ。」
終演後、ライブハウスの店長とおぼしき人間にこう言われたのですが、二人は少し考え込んでしまいました。
「なるほど。だけど、ワンマンのライブをできるほどのお客さんは僕達のバンドにはついていないよ。」
「いや、この日にワンマンライブをするという事は、よほど偉いレコード会社の人が来る日なんだよ。」
「仕方ない、これはチャンスだ。がんばろう。」

ワンマンライブ当日。
親、兄弟、親戚、友達 たくさんの人にお願いして、100人のお客さんに来てもらい、ワンマンライブは大盛況でした。
ただ、レコード会社の人間 とおぼしき人間とは一言も言葉を交わす事はありませんでした。
「スーツ姿の今まで顔を見た事もない人間を、客席の後ろのほうでライブ中に見かけたので、あれがレコード会社の人間だったのかな。」
「そうに違いない。きっと、また後日に連絡があるのだよ。」
「ワンマンライブおつかれさまでした。大盛況でしたね。年末にうちのライブハウスのレギュラー40バンドが出演するイベントがあるので、ぜひ出演してください。」
「お客さんの多いこのライブハウスでやっと僕達もレギュラーのバンドと認められたんだね。」
二人は顔を見合わせ喜びました。
年末のイベント当日。
40バンド出演のイベントとあって、演奏時間は普段より短めの10分ではありましたが、客席はたくさんの人で賑わいをみせていました。
自分達の出番の時間になり、二人はステージにあがり客席を見渡しました。
「あれ。確かに200人近くのお客さんは客席にいてるけど。」
客席にいる人間の顔を見渡して、二人はステージの上で唖然としました。
この日の出演バンド40組のメンバー達だけで、ほぼ客席が埋まっていたのです。
40組の出演バンドがいて、メンバーの平均が4人。
単純計算で 40組×4人=160人
各バンドが1人づつお客さんを呼んでいたとして、そこに+40人
客席には約200人の人。
「今日もおつかれさまでした。イベントもたくさんのお客さんで大盛況でしたね。」
たしかにお客さんが客席にたくさんいてたけど、これを果たしてお客さんと呼んでいいのだろうか。
2人はそこではじめて疑問に思いました。
「お客さんが多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。
来年は新年会イベントもあります。次は約50組が出演予定です。」
なるほど。50組も出演したら確かに客席が人で埋まってはいるかとは思うけど。
顔を見合せました。
「どうもおかしいぜ。」
「僕もおかしいとおもう。」
「つまり沢山のお客さんというのは、ライブハウスにライブを見に来るお客さんの事ではないんだよ。」
「だからさ、このライブハウスにとってのお客さんというのは、僕の考えるところでは、ライブを見に来た人達のことではなくて、出演者の事であって。これは、その、つ、つ、つ、つまり、ぼ、ぼ、ぼくらが……。」
騙されたような気持ちに2人はなってしまい、もうものが言えませんでした。
「いや、いつもわざわざご苦労です。たくさんのお客さんのおかげで、大へん結構なイベントになりました。」
「このライブハウスにとってのお客さんというのは、つまり僕らの事で。バンドがライブハウスにとってのお客さんだったんだよ」
「つまり、お客さんの多いライブハウスというのは、出演してくれるバンドが多いライブハウスって事だったのか。」
ふたりは話しながら、あまりのショックに泣き出しました。
するとライブハウスの奥、事務所の扉の向こうでは、こそこそこんなことを言う声が聞こえてきました。
「だめだよ。もう気がついたよ。もうあのバンド出演してくれないようだよ。」
「あたりまえさ。店長の言いようがまずいんだ。あすこで、”お客さんが多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。”なんて、間抜けたことを言ったもんだから。」
「どっちでもいいよ。どうせ僕らの、給料が上がるわけではないんだ。」
「それはそうだ。けれどももしここへあいつらがもう出演してくれなかったら、それは僕らの責任だぜ。」
「呼ぼうか、呼ぼう。おい、バンドさん、早くいらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。
スピーカーもミキサーも新しくしたし、照明機材だって新しくなりました。楽屋にだってシャワーがつきました。あとはあなたがライブをするだけです。はやくいらっしゃい。」
「へい、いらっしゃい、いらっしゃい。イベントはお嫌きらいですか。フェス形式で2ステージ作るなら1日で60バンドだって出演できますよ。毎月、ワンマンライブをやってくれたってかまわないですよ。とにかくはやくいらっしゃい。」
二人はあんまり心を痛めたために、顔がまるでくしゃくしゃの紙屑かみくずのようになり、お互にその顔を見合せ、ぶるぶるふるえ、声もなく泣きました。
中ではふっふっとわらってまた叫んでいます。
「いらっしゃい、いらっしゃい。そんなに泣いたら、まともに声が出なくなって歌えなくなってしまいますよ。へい、店長、ただいま。毎月、彼らのバンドに自主企画イベントをやってもらえるように交渉中です。さあ、早くいらっしゃい。」
「早くいらっしゃい。」
2人はこのライブハウスに出演する事が、本当に最後のチャンスだと思って出演していたので、裏切られた気分になってしまい、事務所の前で泣いて泣いて泣いて泣いて泣きました。
そのときうしろからいきなり、
「なんなんだ。今日のイベントは。めちゃくちゃじゃないか」という怒鳴り声がして、今日のイベントに出演していたバンドのメンバーの1人が、扉をつきやぶるような勢いで事務所の中に飛び込んでいきました。
事務所から聞こえたライブハウスのスタッフの声はたちまちなくなり、そのバンドのメンバーが、怒鳴リ続けています。
「そもそもお前たちは、僕達の今日の演奏を一目だって見ちゃいないじゃないか。」
「ライブを見ていたんなら、僕達がどんなジャンルのバンドかわかるか。1曲で良いから僕達の曲を歌ってみろよ。」という声がして、それからバリンと何かが壊れる音が鳴りました。
「こんなライブハウスなんて二度と出演しないよ。」と威勢よく帰っていく、そのバンドにひきずられるように二人もそのライブハウスをあとにして、二度と出演することはありませんでした。
半年後。
久しぶりに”お客さんの多い”そのライブハウスの前を2人は通りかかったのですが、入り口には「closed」の札がかかっていました。
どうやら、そのライブハウスは閉店してしまったようです。
もう2人もバンドを辞めてしまっていました。
そしてうしろからは、「久しぶりい、久しぶりい、」と叫ぶものがあります。
振り返ってみると、いつかライブハウスの事務所で怒鳴っていたバンドのメンバーの1人でした。
「久しぶり。いやあ、しかしここは本当に酷いライブハウスだったね。今度、僕たちCDを出すんだ。インディーズだけどね。君達のバンドは最近どう?」
2人は返す言葉もなく、だまっていました。
「”ちょっと有名なライブハウスに出演していたら人気が出る”みたいに考えていたのが、そもそもの間違いだったんだよね。
バンド活動の仕方にテンプレートなんてないのに、人のやり方の真似ばっかりして、誰かに頼ろうとして、自分の頭で考えなかったのが間違いだったのさ。
何よりそんなやり方していても、バンドも音楽も楽しくないしね。楽しまなくちゃね。」
2人はさらに返す言葉がなくなってしまいました。
そして、そのバンドのメンバーと別れた2人は帰り道で顔を見合わせて
「今度こそ、ちゃんとバンドをやってみようか。」
と、どちらからともなく話をしました。
「今度こそ、自分達の頭で考えて、自分達らしいやり方で。」
2人はライブハウスもバンドももう大嫌いだったけど、音楽だけはどうしても嫌いにはなれなかったのです。
「注文の多いバンドマン」ってタイトルで最初は書き出したのですが、途中から「お客さんの多いライブハウス」で内容を思いついてしまったので、内容を変更して、なんとなく適当に書いてみました。
まぁ、今時こんな極端なライブハウスはないと思いますが(笑)。
ちなみに、ライブハウスが悪者みたいな内容になってしまいましたが、ライブハウスも商売なんで、自分の頭で考えないで言われる事をホイホイ承諾していくバンドマンも悪い気はします。
この場合は、ライブハウスもバンドマンもどっちもどっち。
「注文の多いバンドマン」もまた次回以降に機会があれば書きます。